 Menu
Menu
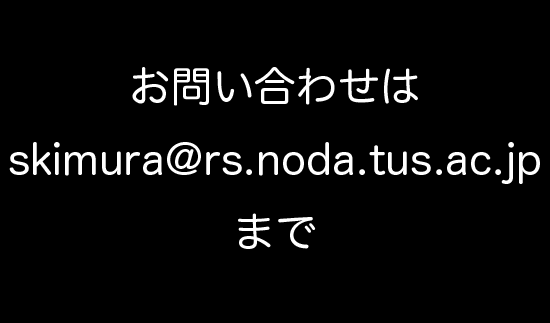
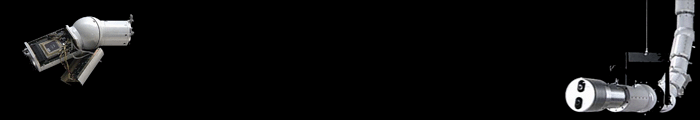
故障しても働き続けるモジュール型ロボット
宇宙空間で衛星の修理をしたり、宇宙のゴミを回収したりするロボットを実現するためには、無重力環境に対応した盛業技術や高真空という極限環境への対応技術、遠隔操作技術などの技術の他に、一つ大事な問題があります。それはロボットの値段です。このことは一見技術的ではないように思えますが、実は技術的な問題でもあります。 宇宙システムは一般に高価だと言われますがそれはなぜでしょうか。人工衛星などは一度宇宙に打ち上げられると、修理することが容易ではありません。ですから、普通は絶対に故障しないように作ります。非常に信頼度の高い設計をし、信頼度の高い過去に実績のある部品を使って、さらにあらゆる可能性について評価試験を行います。こうした開発はどうしても費用がかかるものです。
ところでここで生物のことを考えてみましょう。生物はけがをしても、ゴキブリなどは足をもいでも歩けます。こうした歩行運動はとてもおもしろく、昔馬の歩行パターン(walk,trot,gallopという3つの歩行パターンがあります。)とエネルギー消費量の関係を調べた人がいて、歩行スピードに応じて最適な歩行パターンが実現されていることがわかりました。つまり歩行運動は体全体としてとても合理的に実現されているということになります。ところがこうした歩行運動はなんと脊髄までで実現できるのです。これも有名な実験がありまして、ネコの大脳を取り除いて(小脳も取り除く実験もあります。)基本的に脊髄だけにして、体を支えてやりながらある刺激を与えてやると、なんと猫は歩くのです。歩くだけではなくて、トレッドミルのスピードを変えてやると走ったりするわけです。これを脊髄ネコの歩行実験といいますが、まさに驚きですね。脊髄というのは体の各部分をかなり独立に制御している分散制御系です。分散的な制御系の集まりがどのようにして全体として合理的な運動を作り出すことができるのでしょうか。まさに神秘ですね。
木村は過去に昆虫の歩行に関する研究から、こうした問題を考え、脊髄のように自律分散的なシステムがその時々に協調的に運動を作り出すことで、けがや環境の変化に柔軟に適応する運動を作り出すことができるのではないか考えました。
それでは、こうした生物システムの持つ優れた性質、環境の状況が変わっても、けがをしても、柔軟に適応して目的とする運動を実現できるという考え方を、こうした宇宙で働くロボットにも適応できないでしょうか。つまり、「故障しないシステム」から「故障しても働き続けることのできるシステム」に考え方を変えてみてはどうでしょう。こうした考えで木村はロボットを自律分散的なモジュールから構成するモジュールが他マニピュレータを開発しました。これらのモジュールにはそれぞれ計算機とモーター、お互いに通信する装置が内蔵されていて、電源を入れると、考え、話、勝動くことができます。行ってみればそれぞれのモジュールが自律的なロボットです。これはちょうど先ほど説明した脊髄の構造によく似ていますね。こうした構造にしておいて、マニ?ピュレータ全体の動きを、これらのモジュールに分散的に計算させ、良いものを選ぶことで決めます。このようなシステムを作ることで、部分的な故障が起きてもそのまま作業を続けることができます。
このシステムのおもしろいところは、故障したかどうかこのシステムのなかではだれも考えていないことです。故障状態かどうかの判断はなかなか大変な作業です。このシステムではそれぞれのモジュ?ールはどう動かすかを提案し、その時々で一番いい提案を採用するという方法をとっています。ですから、効率は決して保証されませんが、故障が起きたかどうかを調べることなく、故障に対応した運動を作り出すことができるのです。こうしたモジュール型のロボットをさらに発展していくと、自分で自分の体を修理したり、自分で自分の体を組み立てたりといったロボットも実現できるかもしれません。
 モジュール型ロボット
モジュール型ロボット
 モジュール型ロボットで構成した
モジュール型ロボットで構成した遠隔検査用マニピュレータ
 モジュール型ロボットの内部
モジュール型ロボットの内部