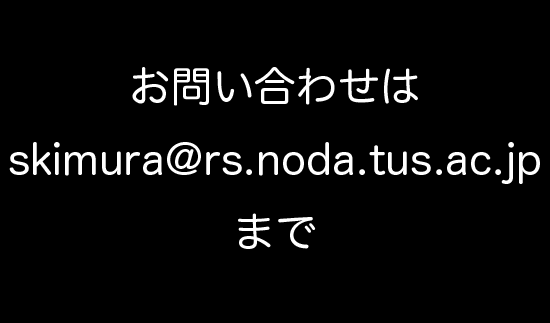研究テーマ
木村研究室は誕生してまもない新しい研究室です。研究テーマも、みんなでアイデアを出しながら考えていきたいと思います。ここでは木村がこれから取り組んでいきたいテーマについてまとめます。一緒に新しい研究室を作る仲間をお待ちしています。
電子技術の目覚ましい発展は、人間と共存する環境など高度な自律性を必要とするロボットや、簡単には手助けのできない環境で働く宇宙システムに大きな変革をもたらす可能性を秘めています。本研究室では、生物の自律性に学びつつ、画像処理技術、自律分散制御技術、ヒューマンインターフェース技術等の研究を中心に、宇宙システムやロボットなど高度な自律制御システムの実現を目指します。ロボットの自律制御技術の研究
生物はけがをしても生きていくために動き続けます。こうした生物のもつしたたかさを実現することができれば、予想もできないような状況に適応できるロボットを実現することができます。木村はこれまで、故障などへの柔軟な対応などロボットの分散知能化について研究を行い、故障にも柔軟に適応できるモジュールロボットを開発してきました。このような研究を拡張し、自分自身を修理し再構成させるロボットや、環境に柔軟に対応するロボット技術について研究を行います。
衛星搭載用高機能カメラの開発
近年デジタルカメラなど、撮像素子や演算素子の開発が盛んに進められています。こうした進歩を宇宙システムに応用しますと、星図をもとにして衛星の姿勢を決定するスターセンサーや、周囲の衛星の画像を用いて相対的な位置を計測し、自律的なランデブーを実現するランデブーシステムなどを実現することができます。木村はこれまで、民生用に開発されたデバイスを宇宙で利用する実験や、ランデブーに必要な画像処理技術などで多くの実績を上げてきました。これらの経験を活用して、コンパクトで高機能な搭載カメラの開発を行い、これを用いた画像処理技術の研究を展開します。
先端技術の宇宙利用に関する研究
近年の急速な電子技術の進歩は宇宙技術にとっても大きなイノベーションの可能性を持っています。これまで宇宙関係の仕事をしてきた視点で見ると、本学科でも宇宙での活用が期待されるユニークな研究が多数行われています。私たちは、これまで、マイクロラブサット1号機での民生品を活用した人工衛星の高知能化・自律制御・画像処理に関する実験を通じて、最先端のデバイスを宇宙で活用する方法について研究を行ってきました。こうした経験を生かして、先端技術を宇宙で活用する方法の研究について進めていきます。
遠隔操作技術の研究
宇宙システムを遠隔操作する際、衛星から送られてくる種々の情報を、リアルタイムに判断する必要があります。これから衛星に期待される機能が高度になり、ロボットの運用など複雑な運用を行うことを考えると、操作者にストレスを感じさせずに、効率良く情報を提示する技術は今後ますます重要になると考えられます。私たちはこれまで実施してきたETS-VIIやMFD、マイクロラブサット1号機などの運用での経験をもとに、人間の心理学特性にまで踏み込んだヒューマンインターフェース技術の研究を進めていきます。
 Menu
Menu