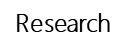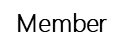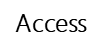研究内容紹介
高分子安定化液晶・反強誘電性液晶の螺旋構造の解析(円偏光二色性、旋光能)
強誘電性液晶や反強誘電性液晶は特徴的な螺旋構造を形成します。様々な高分子を用いて構造を安定化した時、螺旋構造がどのように形成され、どのような特性を発現するのか?
円二色性分散計を用いて、螺旋構造のピッチや螺旋方向などを明らかにしています。
高分子安定化強誘電性液晶の分子配向構造(X線解析)
液晶を構成する分子は、ある次元において結晶と同じように規則性を有した構造を示します。規則的な分子構造はX線を回折するので、X線解析によって液晶分子が並んだ時の規則性が分かります。
これらの規則性を明らかにすることで、新たな液晶分子の物性を探索Sしています。
高分子安定化強誘電性液晶の分子運動(時間分解エリプソメトリ)
液晶材料に電場を印加したとき、液晶分子は電場に対してある向きを揃えるように動きます。強誘電性液晶は、コーン型の分子運動軌道を有するため、電場による分子運動が複雑になっています。
時間分解エリプソメトリを利用することによって、この複雑な分子運動軌道を解析しています。
配向膜のアンカリングエネルギー評価(強電場法)
液晶は界面に設けられた配向膜という有機材料によって、その方向や角度を規制されています。その規制力の強さを”アンカリングエネルギー”と呼び、強電場法などによりその強弱を調べることができます。
配向膜のアンカリングエネルギーから、配向膜自体の物性や、液晶材料への影響を研究しています。
PSCOF(Phase Separated Composite Organic Film)液晶(電気光学効果,誘電分散)
液晶材料は流動性があるため、容器に封入しなければ保持することができません。容器は通常、硬い界面を有してしまいますが、もしも柔らかい界面を用意することができたらどうなるのか?
柔らかい界面を用意するひとつの回答がPSCOF構造であり、その柔らかい界面が及ぼす影響について研究しています。
二量体液晶の分子配向構造解析(偏光FT-IR)
通常の液晶材料には硬い骨格部分が1つしかありませんが、二量体液晶には2つの硬い骨格部分があります。このことを要因として、液晶分子間には相互作用が起こり、様々な並び方(配向構造)を呈するようになります。
偏向FT-IRによって、配向構造を明らかにし、二量体液晶の開拓を進めています。
螺旋構造のコンピュータの解析(Landau-Khalatonikov方程式、コノスコープ)
強誘電性液晶が形成する螺旋構造は、いったいどんな物性が影響しているのか?分子形状なのか?それとも、自発分極の大きさなのか?
実験結果とコンピュータによる解析結果を結び付けながら、その答えを探っています。
高分子安定化液晶(高分子テンプレート、エリプソメーター)
液晶は結晶のような規則性と、液体のような流動性を持ち合わせています。その特性から、まわりの変化に合わせて、様々な分子配向構造を、液晶は自発的に構築することができます。
配向構造を高分子によって固める(安定化)ことで、新たな物性を発現させ、液晶の新しい用途を開拓しています。
古江研究室での生活
方針
ON/OFFのメリハリがある研究生活を目指します。コアタイムはAM10:00~PM5:00です。
アルバイトは自由ですが、大学生活を疎かにしないようことが原則です。
スケジュール
4月:新年度スタート夏休み休暇(お盆を挟んで2週間程度)
9月:ゼミ旅行(行先は幹事の学生が決定)、液晶討論会
10月:研究成果の中間発表
年末年始休暇(正月を挟んで1週間程度)
1月:修論、卒論概要集提出、修論発表会
2月:卒論発表会
3月:応用物理学会、卒業式
※希望者は国際会議にも参加可能です。
古江研での生活
セル作り
液晶を封入するガラス製の液晶セルは、実験を実施する学生が事前に作製を行います。均一な厚みの液晶セルを作ることが重要なのですが、これが非常に難しく、失敗することも多々あります。
また、接着や焼成の作業があるため、1回(10枚程度)を作成するのに1日費やすこともあります。
実験を行うにあたって不可欠なものなので、早いうちにたくさん練習し、コツをつかむ必要があります。
実験
班によって目的は異なりますが、全ての班が偏光顕微鏡という特殊な顕微鏡を使って実験を行います。液晶分子の電場応答や、温度による状態変化を、透過光強度や組織観察によって測定します。
もちろん、1回の実験だけでは失敗したり、良い結果が出ないこともあります。
ゼミ前になって発表する結果が無いなどと慌てないよう、予備日なども考慮した予定を立てて実験するようにしましょう。
研究ゼミ
週に1度、AM10:00からゼミがあります。(時間の変更される場合があります。)それまでの自分の研究成果を資料にまとめて報告し、今後の方針について先生と相談します。
一週間に3人発表します。2ヶ月に1度程度まわってくるので、定期的に結果をまとめておきましょう。
英文ゼミ(B4のみ)
週に1度、B4の必修科目である英文講読があります。古江研では英語で書かれた教科書や論文を読み、訳すことになります。
英語は社会に出ても必要なのでしっかり勉強しましょう。
土曜日&日曜日
土・日は原則として研究室は休みになります。土日はしっかり休んで、翌週に備えましょう。
直上・直下
B4の学生には、指導担当の院生が割り当てられ、研究活動のアドバイスなどを行います。この先輩・後輩の関係を古江研では「直上(ちょくうえ)・直下(ちょくした)」と呼んでいます。