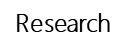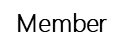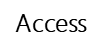液晶の歴史
液晶の発見は、今から1世紀以上前の1888年にさかのぼります。余談ですが、1888年って日本ではどんな事があった頃だか知ってますか?
日本で1888年といえば、明治21年。伊藤博文が日本で最初の総理大臣を務めていました。
東京の上野駅ができたのが1883年。それくらい昔のこと。
ちなみに、東京理科大学ができたのは、明治14年の1881年です。在学生なら常識ですね。
その頃はまだ「東京理科大学」ではなく、「東京物理学校」のさらに前、「東京物理学講習所」という校名でした。
さて、液晶の歴史を紐解いていきましょう。
時は1888年・・・、
液晶はオーストリアの植物学者 Friedrich Reinitzer(ライニッツァー)によって発見されました。
彼は植物学者で、コレステロールについて研究していたのですが、
コレステロールの安息香酸エステルの結晶を加熱していくと白く濁る事を不思議に思いました。
この現象を深く調べたライニッツァーは、安息香酸エステルの結晶を加熱したとき、
145.5℃で溶けて白く粘り気のある液体になり、178.5℃で透明になることを報告しました。
これまでの世界では、1つの物質には1つの融点しか存在しないと思われていました。
しかし、この報告が意味することは、1つの物質に2つの融点が存在するということです。
こうして、2つの融点を持った新たな物質があるという事実が世の中に広まりました。
でも、実のところ、この現象を初めて発見したのはライニッツァーではありません。
もっと前からこの現象は観察されていました。
例えば、ライニッツァーの論文には、Berthelotら数人の研究者が同じような現象を観察していた事が記してあります。
つまり、多くの研究者が2つの融点を持っている物質をすでに調べていたのです。
じゃあ、どうしてライニッツァーが報告するまで、2つの融点があるという事実を報告しなかったのか?
簡単に言ってしまうと、見逃していたのです。
正確に言うと、2つの融点が存在する事は知っていたけれど、それは不純物によるものと思っていた。
つまり、1つの物質が2つの融点を持っている訳では無いって思い込んでいました。
たしかに不純物によるものもいくつかあったかもしれない、でも、そこでちゃんと精製した物質では調べていなかった。
ライニッツァーは、精製した物質を用意して、調べたから不純物じゃないって分かったわけです。
そんなわけで、ライニッツァーはこの不思議な液体を見つけました。
そしてもっと詳しく調べるため、ドイツの物理学者Otto.Lehmann(レーマン)に詳しい研究を任せたのです。
当時、Lehmannは結晶を研究する若手の物理学者でした。
なぜLehmannに研究をお願いしたのか?
それはLehmannが試料を暖めながら顕微鏡で観察できる装置を持っていたからです。
温度によって色や性質が変わるこの不思議な液体の研究にはこの装置が不可欠でした。
ちなみに、この温度によって性質が変わる液晶の事をサーモトロピック液晶と呼びます。
さて、ライニッツァーからレーマンの手に渡ったこの不思議な液体。
レーマンはこの不思議な液体を偏光顕微鏡で観察し、ある現象を確認しました。
それが複屈折という現象。
複屈折は異方性を持つもの、いわゆる結晶でしか起こらない現象です。
ここでちょっと複屈折についての勉強をしましょう。
複屈折というのは、物質の方向によって屈折率などが変わってしまう現象です。
例えば、水を始めとした液体の屈折率は、方向に関係なく同じです。
分かりやすいように球の形をした液体があるとして考えますが、
この場合、どの方向から光を入れても同じ度合いで曲がっていきます。
異方性を持つ結晶は、方向によって屈折率が違うから、このようにはなりません。
球状の結晶に入ってきた光は、異方性の影響によって、屈折の度合いが方向によって変わってしまうのです。
さらには、結晶中での光の速度も方向によって変わってしまう。
結果として、複屈折を示す結晶を通した光は、多くの場合2つに分かれてしまいます。
2つに分かれてしまうために、向こう側が二重に見えることがある。
複屈折ってそういった現象を指すものなんです。
さぁ、液晶の歴史に戻りましょう。
不思議な液体に、複屈折という異方性を持つ結晶独特の性質が見つかったので、
レーマンはこの不思議な液体が結晶の一種だと考えました。
そして液体なのに結晶、つまり液体結晶であると論文に記したのです。
こうしてここに、液体結晶、略して液晶が誕生したのです。
このレーマンの論文が発表されその後の液晶研究は一気に加速していきます。
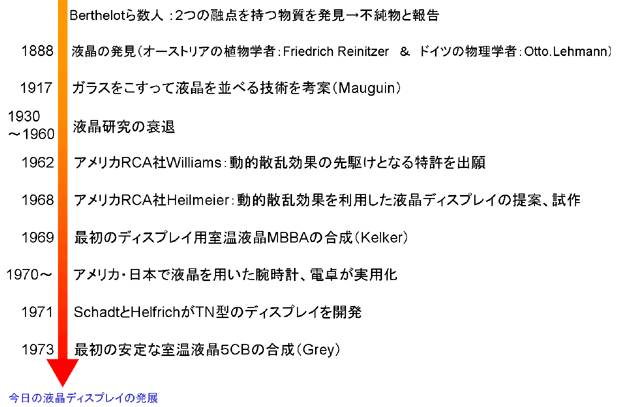
この技術が今のラビング処理の元となっています。
ラビング処理は後で詳しくお話します。
しかし、その後、数十年にわたり液晶研究は衰退してしまいます。
発見当時、液晶はその目新しさもあって、非常に研究が盛んに行われましたが、
いつまで経っても工業製品への応用がほとんどできなかったのです。
製品に応用できないものは、産業界にとって魅力が少ないのです。
そういつまでも製品にならないものは、お金にならないからですね。
その結果として、数十年もの長い低迷期に入ってしまうことになってしまいます。
しかし、数十年の間、液晶研究が衰退したとはいえ、途切れてしまったわけではなかった事は非常に重要な事です。
もし、途切れてしまっていたら液晶ディスプレイなど多くの素晴らしい技術が生まれることはなかったわけです。
さて、液晶が再度研究され始めたのは、みなさんが良く知っている液晶ディスプレイへの応用が始まってからです。
1968年、米国RCA社のHeilmeierが提唱したところから、液晶の大いなる応用へ向けた第一歩が始まりました。
この時に使用された原理は、その提唱の6年前、同社のWilliamsが発見した動的散乱効果を利用したものでした。
動的散乱効果とは、とても大きな電圧をかけた時に液晶が光を散乱するという現象です。
しかし、ディスプレイに利用できたとはいえ、大きな問題が残りました。
この動的散乱効果を利用したディスプレイには大きな電圧が必要になるのです。
大きな電圧をかける事は消費電力が大きいだけではなく、液晶自体の劣化も大きくなります。
これは、長時間の利用を前提としたディスプレイ応用としては致命的な負の要素でした。
そのため、ディスプレイとして実用化されましたが、あまり長くは続きませんでした。
しかし、同時期に、これまで高温でしか存在できなかった液晶に、室温で存在できる液晶が発見されました。
このことが、さらにディスプレイ応用を加速させました。
そして、動的散乱効果を用いたディスプレイの欠点を補うように登場してきたのが、TNモードと呼ばれる方式です。
この表示モードは非常に低電力で液晶を駆動させる事ができるため、今も電卓のディスプレイなどに利用されています。
また、この2年後、ネマチック液晶として室温で安定に利用できる5CBという液晶が合成されます。
この液晶は、液晶を研究する研究者にとって最も有名な液晶のひとつであり、現在も研究などに広く利用されています。
このように、発見から応用されるまで、山あり谷ありの長い歴史を液晶は辿ってきたのです。
特に、液晶研究が衰退しても、その研究の灯を絶やさずに灯し続けてきた多くの研究者の努力というものは、
非常に尊いものであり、忘れてはいけないものだと思います。
液晶ディスプレイが広く普及し、液晶ディスプレイへの応用に限らず、それ以外への模索が続けられている今、
第二の液晶の転換期なのかもしれません。
これまで灯し続けられてきた液晶の灯を次代へつなぎ、新しい液晶の未来を作っていくのは、
古江研究室はもちろんのこと、多くの研究者の方々の努力ではないかと思っています。