液晶ディスプレイの歴史[創世期まで]
『液晶の発見』において、液晶が発見されるまでの事を説明したが、ここでは液晶ディスプレイが実用化されていくまでを説明していこう。
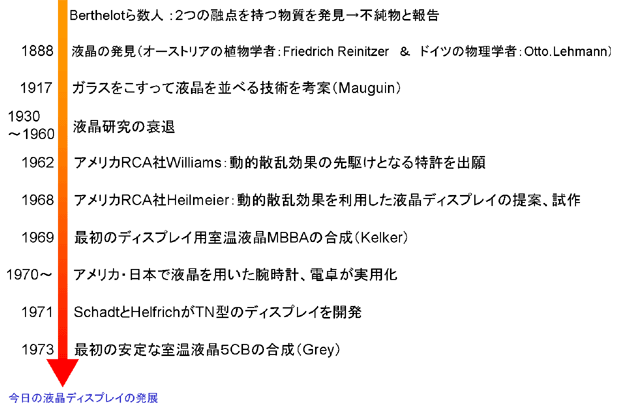 上図におおまかな流れを示しました。
上図におおまかな流れを示しました。1888年、ReinitzerとLehmannによって液晶が発見された事は『液晶の発見』で詳細に述べましたね。
1917年、Mauguinがガラスをこする事で液晶を並べる技術を開発しました。この技術が今のラビング処理の元となっています。
ラビング処理は後の『液晶の配向とラビング処理』で詳しくお話します。
その後、数十年にわたり液晶研究は衰退していきます。
発見当時、液晶という物質はその目新しさもあって、非常に研究が盛んに行われました。
しかし、いつまで経っても工業製品への応用がほとんど考え付かなかったのです。
その結果、液晶研究はどんどん衰退の一途を辿っていきました。
そして数十年の後、液晶がもう一度大々的に研究されるために戻ってくる事になります。
数十年の間、液晶研究が衰退したとはいえ、途切れてしまったわけではなかった事は非常に重要な事です。
もし、途切れてしまっていたら今日の液晶ディスプレイなど多くの素晴らしい技術が生まれなかったわけですから。
さぁ、液晶がまた華やかな研究の世界に舞い戻ったのは、みなさんが良く知っている液晶ディスプレイが1968年にアメリカのRCA社のHeilmeierが提唱した事に始まります。
この時に使用された原理は、その提唱の6年前、同社のWilliamsが発見した動的散乱効果を利用したものでした。
動的散乱効果とは、とても大きな電圧をかけた時に液晶が光を散乱するという現象です。
しかし、ディスプレイに利用できたとはいえ、大きな問題が残りました。大きな電圧が必要になる事です。
大きな電圧をかける事は消費電力が大きいだけではなく、液晶自体の劣化も大きくなり、ディスプレイ応用としては致命的な負の要素でした。
そのため、ディスプレイとして実用化されましたが、あまり長くは続きませんでした。
またそれまで、非常に高温でしか存在できていなかった液晶に、室温で存在できる液晶が発見されました。
このこともディスプレイ応用を加速させていきました。
そして、この動的散乱効果を用いたディスプレイの欠点を補うように登場したのが、TNモードと呼ばれる液晶ディスプレイの方式です。
この表示モードは非常に低電力で液晶を駆動させる事ができるため、今も電卓のような表示の簡単な液晶ディスプレイに利用されています。
また、この2年後、ネマチック液晶として室温で安定に利用できる5CBという液晶が合成されます。
この液晶は、液晶を研究する研究者にとって最も有名な液晶のひとつで現在も研究などに広く利用されています。
このように、発見から応用まで、山あり谷ありの人生を液晶は辿ってきたのです。
特に、液晶研究が衰退しても、その研究の灯を絶やさずに灯し続けてきた多くの研究者の努力は忘れてはいけないものだと思います。
液晶ディスプレイが広く普及し、液晶のディスプレイ応用以外への模索が続けられている今日。第二の液晶の転換期なのかもしれません。
これまで灯し続けられてきた液晶の灯を次代へつなぎ、新しい液晶の未来を作っていくのは僕達大学生や、多くの研究者の方々の努力ではないかと思います。
[参考文献]
液晶のしくみがわかる本 技術評論社 竹添秀男他著 2001