円偏光二色性と旋光能
この章では、光に関する話、偏光の特性に関して、円偏光二色性および旋光能について説明したいと思います。
偏光についてはこれまでいろいろと話してきましたが、直線偏光を分ける場合、円偏光という右回りと左回りの偏光を考えるのが、円偏光二色性と旋光能です。
まずは、旋光能(ORP)について話していきましょう。
ORPは、Optical Rotatory Powerの頭文字をとってそう呼ばれています。つまり、光学的に回転する力。すなわち旋光能です。
回転するというのは、偏光面が回転する事を表しています。
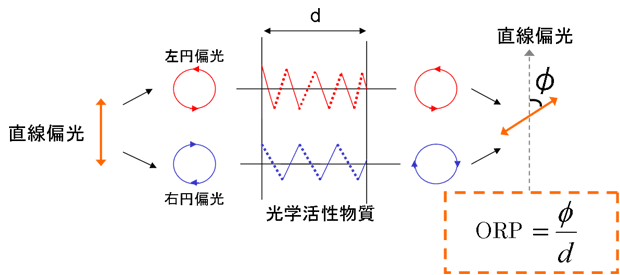 上図のように直線偏光を右回り、左回りの2つの円偏光に分解して考える。
上図のように直線偏光を右回り、左回りの2つの円偏光に分解して考える。光学活性物質(磁場などをかけなくても偏光面を回転させる性質のある物質)に直線偏光が入射した時、右円偏光と左円偏光、それぞれの回転方向の光の屈折率が異なる事から、 物質内でのそれぞれの光の速度に差が生じる。
そのため、物質から出た後の2つの円偏光には位相差が生じています。
そのためその2つの円偏光を合成した直線偏光は、入射した時の直線偏光から角度φだけ偏光面が回転した直線偏光として出てくるのです。
この角度を試料の厚さdで割ったものが旋光能(ORP)なのです。
次に、円偏光二色性(CD:Circular Dichroism)についてお話しましょう。
ORPは屈折率の異方性によるものであったが、CDは吸収率の異方性による現象である。
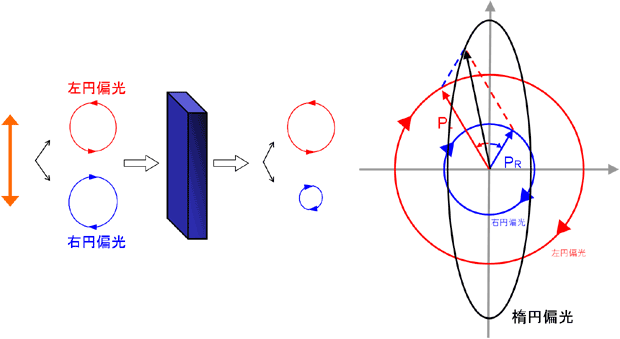 ORPと同じく、直線偏光を左右2つの円偏光の和として考えます。
ORPと同じく、直線偏光を左右2つの円偏光の和として考えます。左右の円偏光に対する吸収率が異なる物質に入射した光が物質を通過した後、出てきた光の大きさは左右で異なります。
その出てきた2つの円偏光の和が出てくる直線偏光であるから、2つの円偏光の和となる偏光は図の右に示したように楕円偏光となります。
この吸収率の異方性による直線偏光から楕円偏光に変わる現象を円偏光二色性と言います。
通常、液晶媒質に入射した光には、このORPとCDの2つの現象が起こり、楕円偏光が作り出されます。
しかし、どんな場合でも楕円偏光になるとは限りません。
次の図を見てもらおう。
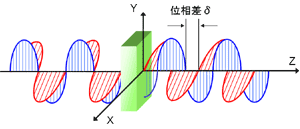 左図は、液晶媒質のような異方性を有する物質を通過したため、δだけ円偏光の位相差がずれたときの模式図である。
左図は、液晶媒質のような異方性を有する物質を通過したため、δだけ円偏光の位相差がずれたときの模式図である。屈折率に異方性が存在する時、この図のように位相差δだけ左右2つの円偏光に差ができてしまう。
この現象が複屈折である。このように位相がずれた2つの光が存在する事から、異方性を有する物質を透過した光が目に入射した時には二重に物質の向こう側が見えてしまうのだ。
また、この位相差がずれた2つの光だが、左図の場合、X軸方向の屈折率が最も低く、Y軸方向の屈折率が最も高いとした場合、X軸方向の光を常光、Y軸方向の光を異常光といいます。 (正確には、どの方向から光が入射しても屈折率が変わらない光を常光、光の入射方向によって屈折率が変化する光を異常光と呼びます。「誘電率・屈折率の異方性」の章で屈折率楕円体の話をしましたが、 一軸性の物質であれば、楕円体の中心を通るどんな断面も一辺(屈折率)がn0の部分が存在しますよね?それが常光が出てくる方向です。逆にニ軸性ではどの断面で切っても屈折率が変化するので出射光の全てが異常光となります。)
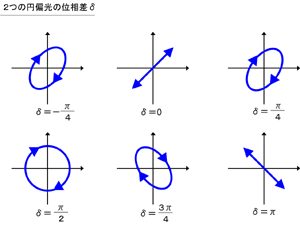 それでは次に左に示した2つの円偏光の位相差δの図を見てもらおう。
それでは次に左に示した2つの円偏光の位相差δの図を見てもらおう。この図で、位相差δによって、出射光がどのような光であるかを示してある。
図を見ると分かるように、δが0とπでは、出射光も直線偏光のままである。つまり、差が0、または一周期であるという事である。
では、それ以外の場合を見てみよう。全て楕円偏光である。ただし、位相差によって方向が異なっている。
液晶ディスプレイに応用する際、このように液晶媒質を通った光が楕円偏光であると非常に困る。
なぜなら、直線偏光でない状態の出射光が出てきてしまうと、ちゃんとした光の制御ができないのだ。
光の制御を行なうには直線偏光だけを取り出さなくてはいけない。そこで、液晶ディスプレイには、この位相差のズレを補正するためのフィルムが組み込まれている。
つまり、位相差δだけずれた楕円偏光をさらに位相差δだけ戻すように位相差をずらすフィルムをつけるのである。
実は、このフィルムも液晶で作られているのである。円盤状の液晶分子で作られた位相差補正フィルムなどが現在使われている。
では、最後に円偏光がらみで選択反射という現象も説明しておこう。
選択反射とは、円偏光の回転方向と螺旋ピッチが、液晶分子の回転方向と螺旋ピッチと等しい場合にのみ、その光が透過せずに反射される現象である。
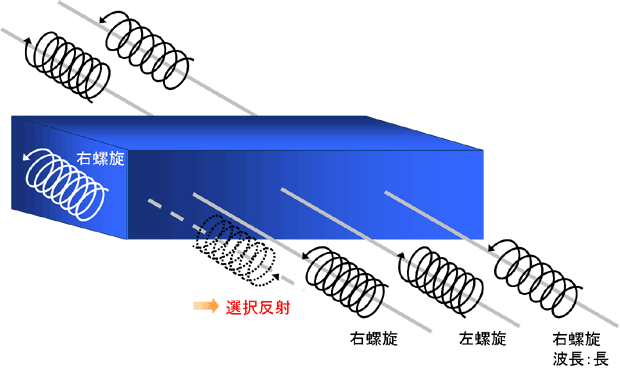 回転方向が異なったり、螺旋ピッチが異なったりすれば、全て透過してしまうため、この媒質の螺旋ピッチを制御する事で、任意の波長の光だけを反射させることができるため、太陽光のような外光だけを利用した光源の要らないディスプレイも実現できるのである。
回転方向が異なったり、螺旋ピッチが異なったりすれば、全て透過してしまうため、この媒質の螺旋ピッチを制御する事で、任意の波長の光だけを反射させることができるため、太陽光のような外光だけを利用した光源の要らないディスプレイも実現できるのである。しかし、実際には様々な問題があり、実用化は今もなされていない。
[参考文献]
液晶とディスプレイ応用の基礎 コロナ社 吉野勝美,尾崎雅則著 1994