分極について
液晶は誘電体であるため、分極という現象は液晶を理解するために必要不可欠なものです。
ここでは、分極について説明していこうと思います。
分極には3つの種類が存在します。
まずは、最もミクロな分極である電子分極について説明します。
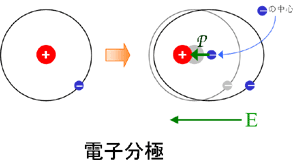 右図のように電子分極は原子内の電子(雲)が、印加電場により、原子核に対して相対変位する事によって起こる分極です。
右図のように電子分極は原子内の電子(雲)が、印加電場により、原子核に対して相対変位する事によって起こる分極です。電場の無い状態では、原子核の位置と電子の存在する中心位置(電子雲の中心)が同じ位置に存在しているため、それらの極性を打ち消しあう事で中性、つまり電荷の偏りが全く無い状態となります。
電場が印加されると、原子核は電場のマイナス方向に引きつけられ、電子はプラス方向へ引きつけられることになります(原子核は電子に比べてはるかに重いため、原子核の変位は無視できる)。
そのため、陽子は無電場時の位置から動き、また電子雲はプラス方向へ引き伸ばされ動きます。
したがって、原子核の位置と電子雲の中心位置がずれ、そのずれが双極子モーメントPを誘起します。
次に、物質内部の原子位置の偏りによるイオン分極(原子分極)を紹介します。
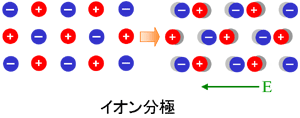 右図にあるようにイオン性物質内(NaClなど)には、プラスイオンとマイナスイオンが等価に存在し、それらが極性を打ち消しあうような規則的な構造(格子構造)を取っています。
右図にあるようにイオン性物質内(NaClなど)には、プラスイオンとマイナスイオンが等価に存在し、それらが極性を打ち消しあうような規則的な構造(格子構造)を取っています。しかし、電場が印加されると、プラスイオンはマイナス方向へ、マイナスイオンはプラス方向へ変位します。正確には、電場がプラスイオン、マイナスイオンの両者が個々に構成している格子(副格子)を歪ませています。
その結果、電荷の偏りができ、双極子モーメントが誘起されるものがイオン分極です。
最後に配向分極です。配向分極は液晶分子を動かすために最も重要な分極です。
配向分極は、電子分極やイオン分極と全く異なる分極です。電子分極やイオン分極は電子やイオンが動く事によって分極を誘起させていました。 動き、つまり変位によって現れる分極なので、これら二つの分極は変位分極と呼ばれます。
しかし、配向分極は変位分極ではありません。
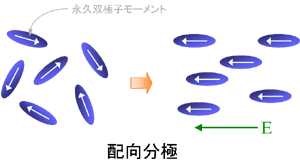 右図にあるように、配向分極は電場を印加することによって分子が持つ双極子モーメントの向きを揃える(配向する)ことによる分極です。
右図にあるように、配向分極は電場を印加することによって分子が持つ双極子モーメントの向きを揃える(配向する)ことによる分極です。双極子モーメントは電場を印加していない時、通常はバラバラな方向を向いています。そのため、双極子モーメントが全体としてそれぞれ打ち消しあっています。
電場を印加させると、その方向に双極子モーメントが方向をそろえるので、双極子モーメントがそれらの総和として誘起されるのです。
3つの分極を説明したところで、次の図を見てもらおうと思います。
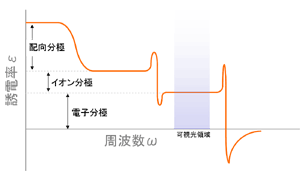 この図は、周波数と誘電率の関係を示しています。
この図は、周波数と誘電率の関係を示しています。言い換えると、どのくらいの周波数でどの分極が誘起されるのかを示しているのです。
高周波では、電子分極しか誘起されないが、低周波になっていくに連れてイオン分極、配向分極と順々に現れていきます。
参考に可視光(約300〜800nm)の帯域を図示しておきました。
可視光の波長域では電子分極しか起こりえません。
もし、可視光の波長で配向分極が起こってしまうと、太陽光や蛍光灯の光などがあるところで液晶ディスプレイを動作させる事ができませんね。
配向分極が低周波でのみ誘起されるからこそ、電圧をかけて低周波の域で誘起される配向分極を用いて動作させているのです。
この配向分極が液晶は流動性があるので、非常に起こりやすいのです。
もし、固体結晶で配向分極を起こそうと思っても、その構造の強固さから分子が配向することが容易にはできません。
このように配向分極が容易に起こしやすいことは液晶の非常に有用な特性と言えますね。
[参考文献]
固体物理 格子振動・誘電体 裳華房 作道恒太郎 1993