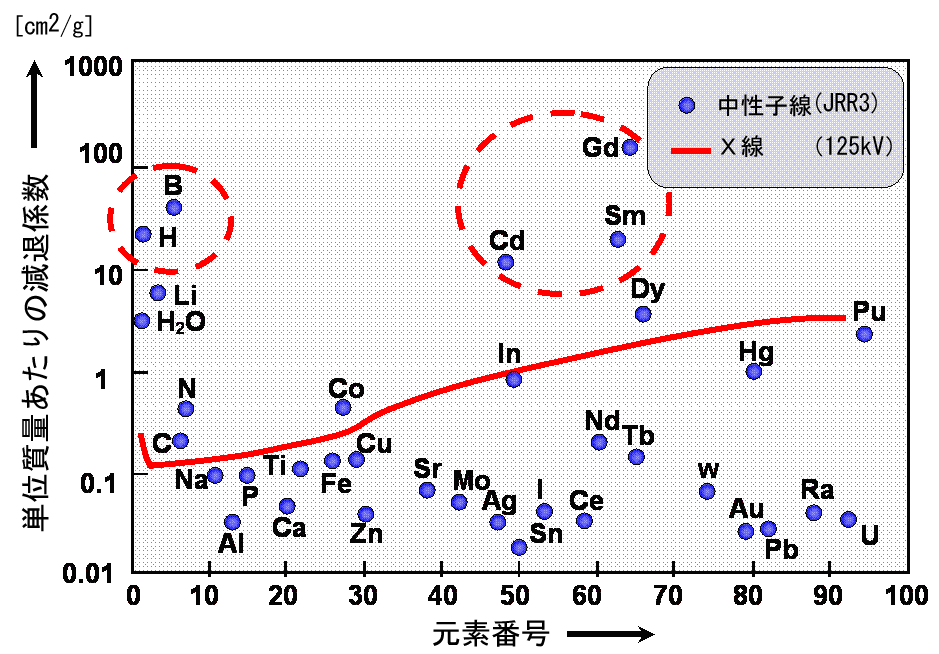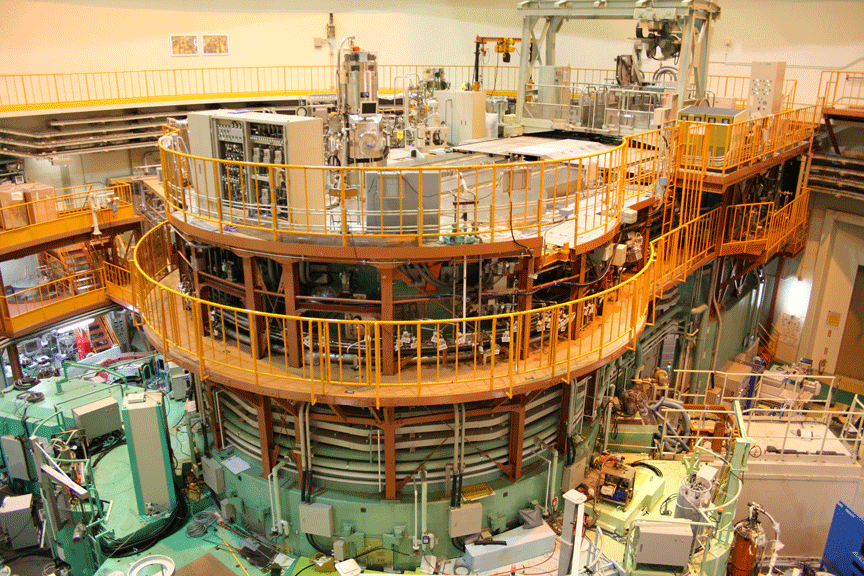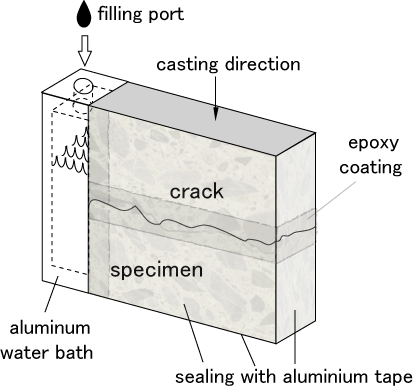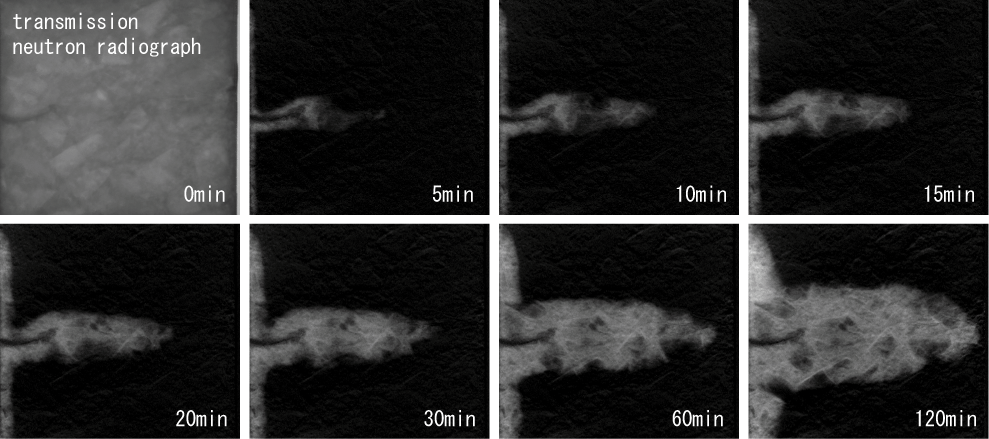|
兼松 学 : 東京理科大学, 野口 貴文 : 東京大学, 丸山 一平 : 名古屋大学, 飯倉 寛 : 日本原子力研究開発機構
|
|||||||
鉄筋コンクリート構造物に生じるひび割れは,水分や劣化因子の移動を容易にし,漏水抵抗性や耐久性に大きな影響を及ぼす.しかし,通常の設計条件下においてはひび割れは不可避なものであることから,ひび割れが物質移動に及ぼす影響を明らかにするために多くの研究がなされて来た.特にひび割れ中の水分移動は,直接漏水に繋がるだけでなく,鉄筋腐食に必要な水分の供給源となることから,ひび割れの影響の中でも重要事項のひとつである.これまでに,表面ひび割れ幅とかぶり厚さと RC 構造物の耐久性との関係を明らかにする多くの研究がなされてきており,これらは許容ひび割れ幅,またはかぶり厚さに応じた許容ひび割れ幅といった概念で整理がなされてきている [1] . 一方,コンクリート中の水分量を捉える手法としては,質量法以外に湿度計などの感知器を埋設する方法が一般的であるが,この埋設手法では,ひび割れ部に代表される局所的現象の実態を測定系に影響を与えずに捉えることは困難であった. そこで,中性子ラジオグラフィを用い,コンクリートのひび割れ中における水分挙動の可視化および定量化を目的とした基礎的な研究を行った。異なる含水率のひび割れ試験体を作成し,一方向から水分を供給して水分挙動の可視化を試みるとともに,局所的含水状態を定量するための解析手法を提案した。その結果,ひび割れ部およびマトリクス中に移動する水分挙動を高解像能で可視化・定量化可能であることが明らかとなった。 |
|||||||
|
|||||||
中性子ラジオグラフィとは,X線ラジオグラフィと同様,中性子線の透過力と減衰特性を利用した非破壊可視化技術のひとつである。 コンクリート工学分野では,一部の研究を除くと原子炉を利用している場合が多かった。ちなみにフレッシュコンクリートの単位水量の測定に早くから用いられている中性子水分計は,放射線源として放射性同位元素の252Cf (カリフォリウム)を利用した装置である。 中性子ラジオグラフィの撮影には,コンバータやシンチレータと呼ばれる中性子を荷電粒子や光に変換するセンサが用いられ,主に直接法,間接法,実時間撮影法に分類される19)。実時間撮影法(図2)は,中性子線が可視光に変換されることから通常の光学系のカメラにより撮影可能で,動画などの撮影が行われるなど適用事例も多い。 空間分解能は勿論装置仕様に依存するが, おおよそ100μmから1000μm程度である場合が多い。また,時間分解能は,実時間撮影法の場合は用いるカメラまたはビデオのシャッタースピードやフレームレートに依存するため,撮影機器の選択により比較的自由に選択できるが,一般に時間分解能を小さくとると取得画像は暗くなる。一方,直説法や間接法の場合はデータ転送時間などを含めて数秒から数十秒程度が一般的である。近年では,画像の取得・処理技術の高度化が進み,CT技術を用いた3次元可視化など,新しい試みがなされるようになってきている。
|
|||||||
|
|||||||
予備実験などから,セメント硬化体中の水分挙動の定量性はペーストレベルで保証されることが明らかとなっており,厚さ数cm程度の試験体であれば,コンクリート中の水分挙動を定量的に議論することが可能であることが明らかとなっている. 用いたコンクリートの調合は, W/C を 50% とし,含水率を 0% , 30% , 60% の 3 水準とした. 中性子ラジオグラフィによりイニシャル値を測定した後,上部孔よりビニルチューブにて水分を注入し水槽を満水にし,注水前後よりおおよそ 8 秒間隔で 2 時間まで撮影を行った.ひび割れ部を移動する水分のみを可視化するため,各時刻の画像と注水時の水分強度の差分画像を作成し検討した ( 図 -2) .ただし,水槽中の水分の中性子散乱効果が見られたため,差分をとる注水時の画像には,水槽が満水になった直後の画像を用いた. 図-3に試験結果の一部を示す.また,得られた画像を時系列に従い連続的に表示するよう加工した動画を,動画-1に示す.
|
|||||||
|
|||||||
■ 中性子ラジオグラフィを用いて,骨材からの水分移動の定量化について名大丸山先生らが検討した事例はこちら! ■ 発表論文 1) 兼松学,丸山一平,野口貴文,飯倉寛,松林政仁:中性子ラジオグラフィによるコンクリートのひび割れ部の水分挙動の可視化,セメントコンクリート研究討論会論文集,pp.17-22,2006.11
|
|||||||
|
|||||||
|
藤本郷史(ポストドクター研究員) 日本大学 辻埜真人(東京大学 博士課程3年) 他,東京大学野口研究室 のメンバー |